
債務整理

債務整理
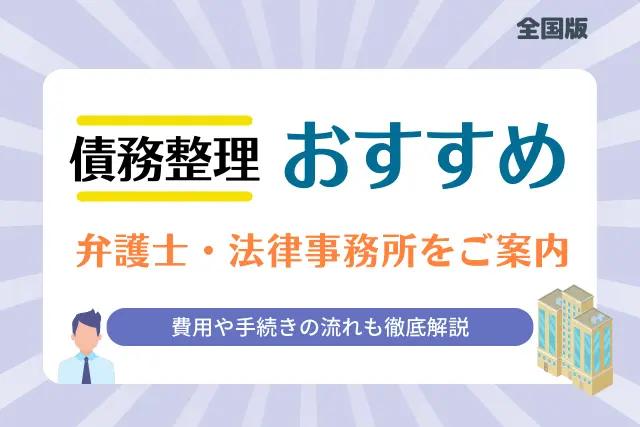
本ページはPRが含まれています。
複数企業と提携し当サイトを経由してサービスの申込が行われた際は、提携企業から対価を受け取ることがあります。ただしランキングや評価に関して、有償無償問わず影響を及ぼすものではございません。

毎月の返済が苦しい…

複数の会社から借金があり、どこから手をつければいいか分からない

債務整理をしたいけど、費用が払えるか不安だし、どの事務所を選べばいいか…
借金問題は、一人で抱え込んでいても解決が難しいケースがほとんど。ですが、弁護士に相談することで、督促を止め、法的な手続きに則って借金を減額・免除できる「債務整理」という解決策があります。
とはいえ、いざ弁護士を探そうにも、
費用はいくらかかるの?
どの事務所が本当に信頼できるの?
自分にはどの手続き(任意整理・個人再生・自己破産)が合っているの?
家族や会社に内緒で手続きできる?
など、次から次へと疑問や不安が湧いてくるのではないでしょうか。
この記事では、債務整理を検討する際に知っておくべき情報を網羅的に解説します。あなたが後悔しない弁護士事務所を選び、新しい生活への一歩を踏み出すための道しるべとなれば幸いです。
【注意】 本記事は、債務整理に関する一般的な情報提供を目的としており、法的アドバイスではありません。個別の状況については、必ず弁護士にご相談ください。
債務整理で実績多数の弁護士事務所や司法書士事務所を一覧にしました。それぞれ、オンライン相談やLINE相談が可能かどうかなど、特徴が一覧で分かるようにしています。どこに相談しようか迷った際は、こちらから検討してみては如何でしょうか?
債務整理の成否は、パートナーとなる弁護士事務所選びにかかっていると言っても過言ではありません。ここでは、相談・依頼する前に必ず確認すべき10の基準を、チェックリスト形式でご紹介します。
最も重要なのが費用の透明性です。契約前に、総額でいくらかかるのか、その内訳はどうなっているのかを明確に説明してくれる事務所を選びましょう。
法律相談にかかる費用。無料の事務所が多いです。
弁護士が業務を開始する際に支払う費用。手続きの結果に関わらず発生します。無料の事務所もあります。
手続きが成功した場合に支払う費用。「基本報酬」と「減額報酬」があります。
手続きを進める上で必要となる費用(裁判所への予納金、印紙代、郵便切手代など)。
債務整理を検討している方は、手元にまとまったお金がないケースがほとんどです。そのため、弁護士費用の分割払いや後払いに対応しているかは非常に重要なポイントです。
また、収入や資産が一定基準以下の方は、国が設立した法的トラブル解決の窓口である「法テラス(日本司法支援センター)」の民事法律扶助制度を利用できます。この制度を使えば、弁護士費用の立替え払いが可能になります。法テラスの利用に対応している事務所かどうかも確認しましょう。
多くの事務所が初回相談を無料としています。まずは無料相談を活用し、複数の事務所の話を聞いて比較検討するのがおすすめです。その際、以下の点も確認しておくと良いでしょう。
遠方の方や、日中忙しい方にとっては、オンライン相談の可否も重要な選択基準になります。
相談時には弁護士が対応してくれたのに、契約後は事務員としか話せない、というケースも残念ながら存在します。債権者との交渉や裁判所への対応など、重要な局面で弁護士本人がどこまで直接対応してくれるのかを契約前に必ず確認しましょう。
債務整理は非常に専門性の高い分野です。医師に内科や外科といった専門分野があるように、弁護士にも得意な分野があります。
公式サイトで実績を確認したり、相談時に直接質問したりして、債務整理に関する経験と知識が豊富な事務所を選びましょう。
信頼できる弁護士は、手続きのメリットだけでなく、デメリットまできちんと説明してくれます。特に、信用情報機関に事故情報が登録されること(いわゆるブラックリスト状態)や、手続きごとの制限事項など、依頼者が不利益を被る可能性についても包み隠さず話してくれるかは、誠実さを見極める重要なポイントです。
依頼後、手続きがどのくらい進んでいるのか分からず不安になる、という声は少なくありません。
スムーズにコミュニケーションが取れる事務所を選ぶことで、手続き中の精神的な負担を軽減できます。
弁護士は、各都道府県の弁護士会に所属することが義務付けられています。過去に業務上の問題で「懲戒処分」を受けていないかを確認することで、リスクを避けることができます。所属する弁護士会と弁護士氏名が分かれば、日本弁護士連合会(日弁連)のサイトで検索が可能です。
インターネット上の口コミや評判は参考になりますが、全てを鵜呑みにするのは危険です。匿名性の高いサイトでは、意図的な高評価や誹謗中傷が書き込まれている可能性もあります。
あくまで参考情報の一つと捉え、最終的には自分自身が無料相談で感じた印象を最も重視しましょう。
契約書は、事務所とあなたの約束事を記した最も重要な書類です。サインをする前に、以下の点が明確に記載されているかを必ず確認してください。
少しでも不明な点があれば、納得できるまで質問し、その内容を書面に残してもらうようにしましょう。
[ ] 費用体系(着手金・報酬金など)がホームページやパンフレットで公開されているか?
[ ] 費用の分割払いや後払いに対応しているか?
[ ] 法テラスの利用は可能か?
[ ] 初回相談は無料で、時間も十分か?
[ ] オンラインや電話での相談に対応しているか?
[ ] 重要な交渉や手続きを弁護士本人が担当してくれるか?
[ ] 債務整理の解決実績(件数など)は豊富か?
[ ] デメリット(信用情報への影響など)もきちんと説明してくれたか?
[ ] 連絡手段が明確で、進捗報告の頻度についても説明があったか?
[ ] 契約書の内容が明確で、不明点がないか?
債務整理には、主に「任意整理」「個人再生」「自己破産」の3つの手続きがあります。どの手続きが最適かは、借金の総額、収入、財産の状況などによって異なります。それぞれの特徴を理解し、自分に合った方法を見つけましょう。
手続きの種類 | 任意整理 | 個人再生 | 自己破産 |
借金の減額幅 | 将来利息のカットが中心 | 元本を大幅に減額(約1/5~1/10) | 全額免除(税金等を除く) |
裁判所の関与 | なし(裁判外での交渉) | あり | あり |
財産の処分 | 原則不要 | 原則不要(住宅ローン特則あり) | 一定以上の財産は処分対象 |
手続きの対象 | 交渉する債権者を選べる | 全ての債権者が対象 | 全ての債権者が対象 |
資格制限 | なし | なし | 一部の職業・資格に制限あり |
信用情報登録 | 約5年 | 約5年~10年 | 約5年~10年 |
向いている人 | ・比較的借金額が少ない | ・借金額が大きい | ・返済能力がない |
任意整理は、裁判所を通さず、弁護士が債権者(貸金業者など)と直接交渉し、将来発生する利息(将来利息)や遅延損害金をカットしてもらい、減額後の元本を原則3~5年で分割返済していく手続きです。
個人再生は、裁判所に申し立てを行い、再生計画の認可を受けることで、借金の元本を大幅に減額(通常は5分の1程度、最低100万円まで)してもらい、その金額を原則3年(最長5年)で分割返済していく手続きです。
自己破産は、裁判所に申し立てを行い、支払い不能であることを認めてもらうことで、税金などの一部の債務を除き、原則として全ての借金の支払い義務を免除(免責)してもらう手続きです。人生をゼロから再スタートさせるための最終手段と位置づけられています。
手続き期間中、弁護士、司法書士、警備員、生命保険募集人など、一部の職業に就けなくなります(免責許可が確定すれば復権します)。
特定調停とは、弁護士などに依頼せず、自分で簡易裁判所に申し立てを行い、調停委員の仲介のもとで債権者と返済条件について話し合う手続きです。費用が安い(1社あたり数千円程度)のが最大のメリットですが、以下の注意点があります。
専門知識がない場合は、弁護士に依頼する方が確実で、結果的に有利な解決につながることが多いです。
債務整理を行うと、信用情報機関(CIC、JICC、KSC)に事故情報が登録されます。これが、いわゆる「ブラックリストに載る」という状態です。この期間中は、新たにクレジットカードを作成したり、ローンを組んだりすることが原則できなくなります。
この期間はあくまで目安であり、金融機関によって判断は異なります。
「弁護士に頼みたいけど、費用が払えない…」という不安は、債務整理をためらう大きな原因です。ここでは、手続きごとの費用相場と、無理なく支払うための方法を詳しく解説します。
任意整理の費用は、交渉する債権者の数によって変動するのが一般的です。
【計算例】 3社から合計200万円の借金を任意整理した場合
裁判所を介すため、任意整理よりは高額になります。
手続きの種類によって大きく費用が異なります。
弁護士費用とは別に、手続きに必要な実費が発生します。
多くの弁護士事務所では、費用の分割払いに対応しています。弁護士に依頼すると、債権者への返済が一時的にストップするため、その間に浮いたお金を弁護士費用の積立てに充てることができます。後払いに対応している事務所もあります。
ただし、債務整理の対象となるクレジットカードでの支払いはできないので注意が必要です。
収入や資産が一定の基準を下回る方は、「法テラス(日本司法支援センター)」の民事法律扶助制度を利用できます。
利用できるかどうかは、お近くの法テラスや契約弁護士に確認してみましょう。
弁護士との初回相談をスムーズかつ有意義なものにするために、事前の準備が重要です。
正確な情報がなくても相談は可能ですが、以下の情報を用意しておくと、弁護士がより具体的なアドバイスをしやすくなります。
相談時には、遠慮せずに疑問点を全て解消しましょう。後々のトラブルを防ぐためにも、以下の質問は必ず確認することをおすすめします。
債務者の弱みにつけこむ悪質な事務所もいるかもしれません。大切な手続きを任せる前に、怪しいサインがないかを見極めましょう。
「今日中に契約すれば安くなる」などと契約を急がせたり、費用の内訳を明確にせず「全部込みで〇〇万円」といった不透明な説明をしたりする事務所は要注意です。
過払い金がないにもかかわらず高額な減額報酬を請求したり、契約時には説明のなかった「事務手数料」「通信費」などの名目で後から追加費用を請求したりするケースがあります。
公式サイトに代表弁護士の氏名や経歴、弁護士会登録番号が明記されていない事務所は避けましょう。懲戒処分歴を正直に公開していない場合も同様です。
「100%成功」「誰でも借金がなくなる」といった断定的な表現や、過度に不安を煽るような広告を出している事務所は、依頼者を集めることだけが目的である可能性があります。
安全を確認する最も確実な方法は、公的情報をチェックすることです。 日本弁護士連合会(日弁連)のウェブサイトにある「弁護士情報検索」ページで、弁護士の氏名や事務所名を入力すれば、登録情報や過去の懲戒処分歴の有無を確認できます。相談前に一度調べておくと安心です。
依頼してから生活が落ち着くまで、どのようなステップを踏むのか、全体像を把握しておきましょう。
債務整理はゴールではなく、新たなスタートです。手続きによって返済の負担がなくなった(または軽くなった)後は、二度と同じ状況に陥らないよう、家計管理の習慣を身につけることが重要です。多くの弁護士事務所では、手続き後の生活再建に関するアドバイスも行っています。
債務整理に関して、特に多くの方が疑問に思う点をまとめました。
原則として、バレる可能性は低いです。 弁護士からの連絡は本人宛に行われ、裁判所からの書類も弁護士事務所経由で受け取れます。ただし、以下のようなケースでは知られる可能性があります。
債務整理の対象としたカードは、受任通知を送付した時点ですぐに解約となります。対象としなかったカードも、更新時などに信用情報を照会され、いずれ利用できなくなる可能性が高いです。 信用情報から事故情報が消えるまでの約5年~10年間は、基本的に新たなクレジットカードの作成や利用はできません。その間は、デビットカードや家族カード、プリペイドカードなどを利用することになります。
信用情報が回復するまでの約5年間は、新たな借入れは非常に困難です。そもそも債務整理は、借金に頼らない生活を再建するための手続きです。安易に借金を繰り返さないよう、家計管理を徹底することが重要です。
信用情報への影響などデメリットは確かにありますが、それ以上に大きなメリットがあります。
司法書士も債務整理を扱えますが、弁護士との間には明確な違いがあります。
借金問題は、時間とともに利息や遅延損害金が膨らみ、状況は悪化する一方です。一人で悩み、返済のために新たな借金を繰り返す前に、まずは専門家である弁護士の無料相談を利用してください。
この記事で解説した「弁護士事務所を選ぶ10の基準」を参考に、複数の事務所に相談してみましょう。実際に弁護士と話すことで、人柄や相性、説明の分かりやすさを肌で感じることができます。
「費用が明確で、分割払いに応じてくれるか」 「自分の状況に合った手続きを、メリット・デメリット含めて提案してくれるか」 「この人になら任せられる、と心から思えるか」
これらの点をしっかり見極め、あなたが納得できるパートナーを見つけることが、生活再建への最も確実な第一歩です。勇気を出して、相談の電話をかけてみてください。あなたの未来は、きっとそこから変わります。
全国の債務整理情報
注目の都市の債務整理情報
札幌市 函館市 旭川市 青森市 弘前市 八戸市 盛岡市 仙台市 秋田市 山形市 福島市 会津若松市 郡山市 いわき市 水戸市 宇都宮市 前橋市 高崎市 さいたま市 川越市 熊谷市 川口市 千葉市 市川市 船橋市 松戸市 新宿区 世田谷区 渋谷区 杉並区 豊島区 北区 板橋区 練馬区 八王子市 横浜市 川崎市 相模原市 新潟市 長岡市 富山市 高岡市 金沢市 福井市 敦賀市 甲府市 長野市 松本市 上田市 岐阜市 静岡市 浜松市 名古屋市 豊橋市 岡崎市 津市 四日市市 大津市 彦根市 京都市 福知山市 大阪市 堺市 神戸市 姫路市 尼崎市 明石市 西宮市 奈良市 和歌山市 鳥取市 米子市 松江市 浜田市 出雲市 岡山市 倉敷市 広島市 呉市 福山市 下関市 宇部市 山口市 徳島市 高松市 松山市 今治市 高知市 北九州市 福岡市 大牟田市 久留米市 佐賀市 長崎市 佐世保市 熊本市 大分市 宮崎市 鹿児島市 那覇市